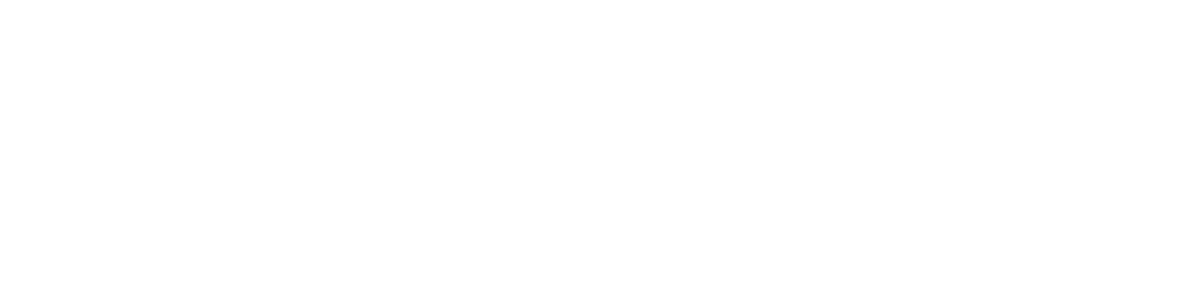福島に寄り添い、原子力災害医療の実効性確保をめざして
2011年3月11日に、東日本大震災、そして東京電力福島第一原子力発電所事故が起こりました。当時「想定外」とされた事故への対応を通じ、私たちは不測の事態に備える必要性を自覚するとともに、危機管理体制の重要性を再認識することとなりました。
その後、新たな原子力災害医療体制を構築するため、2015年に原子力規制委員会が「高度被ばく医療支援センター」と「原子力災害医療・総合支援センター」を指定しましたが、本学もその一つとなりました。当初指定されたのは5か所(量子科学技術研究開発機構*、弘前大学、福島県立医科大学、広島大学、長崎大学)ですが、2023年から福井大学*も指定されました。支援センターは、原子力災害時において、原発立地道府県等で指定されている原子力災害拠点病院が対応できない被ばく傷病者等を受け入れるとともに、被災地へ原子力災害医療派遣チームや専門家を派遣します。また、平時においては、研修・訓練等を通じ、原子力災害医療関係者との連携体制を構築するとともに、原子力災害医療に精通した人材の育成を行っております。
原子力災害対策戦略本部は、本学が支援センターとしての責務を果たすため、2016年に設置されました。原子力災害時、国は「原子力災害対策本部」を設置しますが、平時から備える、被災直後からの現地に継続的に寄り添う、そのために本学は対策本部を常設する、そういった理念のもと、「常に備えよ(Be prepared)」の精神のもと「原子力災害対策戦略本部」と名付けられました。その理念は現在も当本部構成員へ引き継がれております。
長崎への原爆投下、チョルノービリ事故、東京電力福島第一原子力発電所事故を通じて本学が向き合った被ばく医療の経験を、「被災地の復興」と「平時の備え」につなげるため、我々は関係機関との協働・連携支援の下、管轄する九州4県(佐賀、長崎、福岡、鹿児島)を中心とした皆さんの安全・安心を担保するため、責任を果たしてまいりたいと思います。
(2024年4月)
*量子科学技術研究開発機構、福井大学は、高度被ばく医療支援センターのみ指定されており、量子科学技術研究開発機構は基幹の位置づけです。